
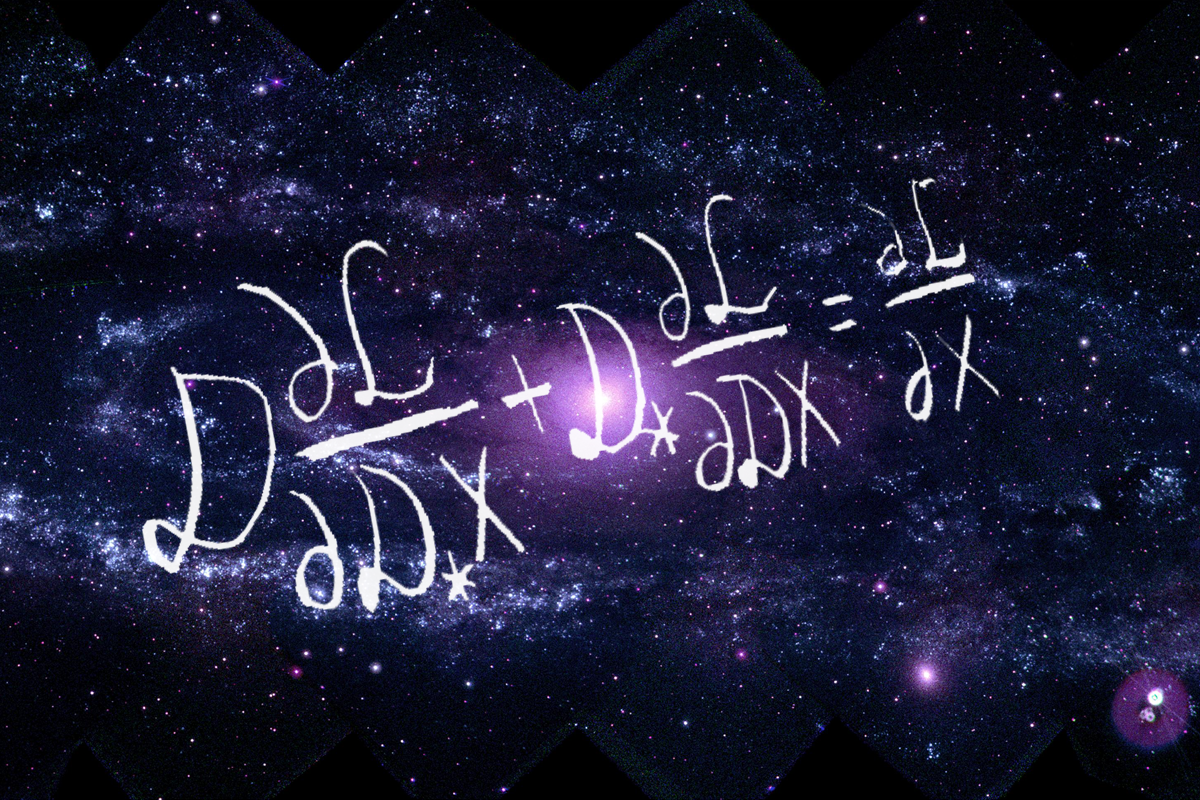
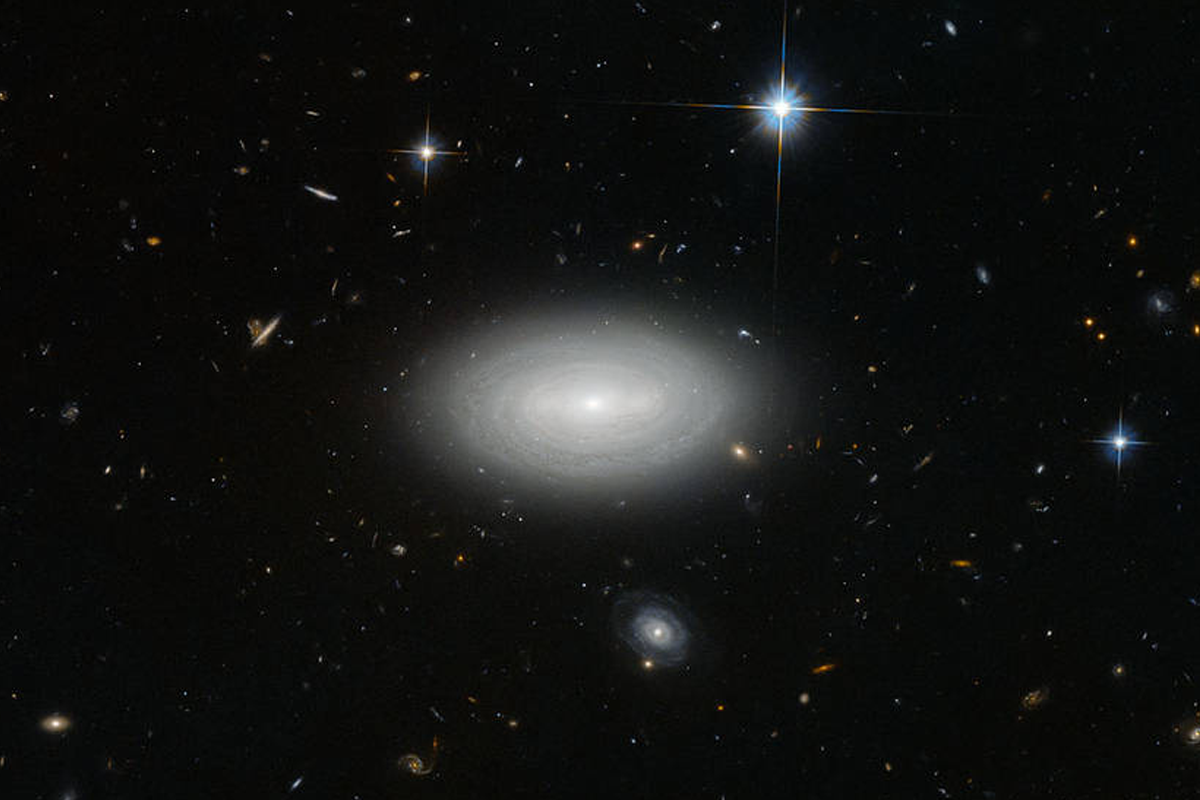


しばらく前のこと、『レトロ東京』と題して港区白金界隈に残る古き良き東京の姿をご紹介しました。それを読んで下さった方の中には、港区にそんなところが本当にあるのか信じられないといった声を寄せて下さる方も少なくはありません。特に岡山からは、『レトロ東京』だけでなく最後まで溶けないかき氷を出してくれる甘味処が東京の下町にあるということをお知らせしたことに対しても、岡山の老舗「カニドン」以外にそんなかき氷があるわけがないとの意見を頂戴したこともあります。
そんな疑問をぶつけられたままでは、心穏やかに過ごすこともできない小心者の僕は、その後街中を歩くたびに僕の言葉が正しかったことを示す証拠集めを忘れることはありませんでした。白金商店街からはマンションに隠れて見通すことができませんが、ほんの数メートル入ったところにはかなり古い二階建ての家をすぐに見つけることができます。

如何でしょうか? 未だにこのような懐かしい家が現役で使われているのですよ、港区白金というところは。そして、つい先日のこと。これまた以前ご紹介したレインボーブリッジの夜景を眺めるため、日が暮れてからコンテナ埠頭のほうに出かけました。ライトアップされた美しい吊り橋の下を通過していく漁船もまた、昼間に見るよりもはるかに輝いています。

その帰りのことでした。偶然にも、『レトロ東京』でご紹介した古くて珍しい外観のアパートの前を歩いていたとき、一階と二階の廊下らしきところに照明がついていました。おまけに、風通しをよくするためか、右側の入り口ドアが開いていて、少しだけ中の様子が外からうかがえたのです。まるで僕のことを招き入れるかのように。せっかくのお招きにあずかり、僕はそのレトロなアパートの共有部分を見学(?)させてもらうことにしました。

入り口ドアから覗いた一階の廊下は意外に明るい照明で、両側に並んだ部屋のドアや電力計が整然と配置されているのが見て取れます。僕が大学生だった昭和四十年代に多かった大学生向けのアパートの典型的な造りですが、そうすると築五十年以上は経っているということになります。

外から中に入ったすぐのところには「電話室」と記された黄色いドアの箱部屋があり、当時はここにピンク色の公衆電話が置かれていたであろうことを想像することができます。僕の親父の夢は息子である僕を慶應義塾大学の法科に入れて役人にすることだったのですが、UFOと宇宙人に興味を懐いていた僕はそんな親父の夢を砕くかのように、遠く仙台にある東北大学の天文学科に進学してしまいました。もしも僕が親父の希望どおりに慶応大学に進んでいたなら、法科のある三田のキャンパスに通っていたことになり、ひょっとすると当時新築なったばかりのこの学生アパートで四年間を過ごしたかもしれない・・・。そんなことをふと考えてしまったのは、未だに親父に対して後ろめたく思っているからかもしれません。
しかし、親父の言いなりになって高校卒業と同時に東京のど真ん中に出てきていたなら、きっと情けない僕はこの電話室から親父に泣きの電話を入れていたに違いありません。あの頃の僕には、岡山よりはほんの少しだけ都会だった仙台の街がちょうどよかったと、今でも信じているくらいですから。

電話室の手前にあった階段を上ってみると、最初に目につくのは上がりぶちに掲げられた「石油ストーブ厳禁」という赤い警告札です。そういえば、仙台で僕が四年間入っていた学生アパートでも石油ストーブは禁止で、電気炬燵と電気ストーブだけで寒い冬を過ごさなくてはなりませんでしたから、この警告札もこの学生アパートが建てられたときからここにあるのでしょう。

当時の僕の部屋代は月に四千五百円でしたが、現在のこの学生アパートの家賃はいったい幾らくらいなのでしょうか? 確か当時の大学の学生食堂では百円で充分に食べることができましたが、今では五百円は必要でしょう。ということは、五十年ほど前に比べて学生生活の物価は五倍になっていると考えれば、二万円ちょっとというのが適切な家賃かもしれませんね。
そっと音を立てないようにして二階に上がってきた僕が廊下を覗いてみると、一階の廊下と同じような光景が広がってきます。

まるで学生時代にタイムトラベルしたかのような光景にしばし酔っていた僕は、それでも港区白金には未だにこのような懐かしい学生アパートも健在しているという証拠として、廊下や電話室の様子を写真に収めることを忘れてはいませんでした。
翌日のこと、前夜のレトロ東京探検で気をよくした僕は、その勢いを駆って愛車のミニクーパーを飛ばし、溶けないかき氷を出してくれる下町の甘味処まで行ったのです。その目的は、もちろん溶けないかき氷の証拠写真を撮影するためです。
注文したのは「ミル金」ではなく、ミルクはかけない「氷あずき」。「ミル金」ではなく「氷あずき」にしたのは別に他意はなく、単にそのときの気分でそうしただけです。まあ、気分屋の僕のことですから、いつものことだと思って許してやって下さい。
ということで、僕の注文した「氷あずき」が出てきてから食べ終わるまでの容器の中の一部始終を撮影しましたので、本当に「溶けない」ということを写真でご確認下さい。
まずは、テーブルに置かれたときの涼しげな雰囲気をご覧あれ。

特に小豆の上の氷が薄い帯状になっている点にご注目いただけると、このかき氷が何故溶けにくいのかがわかります。そう、岡山の「カニドン」のかき氷と同じで、氷を小さく砕くように削っているのではなく、鋭いカンナで木や鰹節を削るのと同じで氷を鰹節のように薄く削ぎ落としているため、氷が断熱材の空気に包まれているのです。

容器の底が見えるよう、スプーンで穴を掘っていくように食べ進みます。

どうです、もう半分以上食べ終わりましたが、容器の底にはまったく溶けた水分が見えませんね。

もう残りわずかですが、ほら、見事に溶けていませんよ!

さあ、最後の一口を残すだけになっても、その一口は溶けた水分などではなくちゃんと氷のままの状態です! これでおわかりいただけたと思いますが、この甘味処のかき氷も岡山の「カニドン」と同じく正真正銘の「溶けないかき氷」なのですよ。
レトロな東京自慢(?)の再確認のシメは、白金にある「三丁目の夕日」に出てくる「鈴木オート」のような街の自動車屋さんにお願いします。今年の二月に岡山から666キロメートルを走破して東京に持ち込んだ真っ赤なミニクーパーですが、その後の半年間で都内を走り回った上に先日は気仙沼から秋田を経て仙台と福島の会津から群馬の高崎を回ってから東京に戻る、総計1000キロメートルのロングドライブにも耐えてくれました。ということで、中古で購入してから半年で2000キロメートルも走らせてしまったため、そろそろエンジンオイルを交換するだけでなくタイヤもローテーションさせたりブレーキも点検しなくてはならないタイミングになってしまいました。
ネットで調べてみると東京都内中心部には三軒ほどのミニ専門の大きな自動車屋があるようで、岡山からミニを持ってくるときにはその三軒の中のどの店かに点検や修理に持ち込むつもりでした。しかし、三軒とも車で三〇分は走らないといけない場所にあったため、点検に持ち込んだ帰りには代車が必要になってしまいます。それがいささか面倒で、なかなか持ち込めずにいたところ、白金の僕の部屋から歩いて五分のところに「鈴木オート」的な自動車屋さんがあるのを見つけました。しかも、修理や点検に並んでいるのはほとんどが外車ばかり。それならと思って、お店の方にうかがったところ前のミニクーパーでも扱えますとのこと。

それではお願いしますということになったのですが、その店には絶えず港区白金や南麻布界隈に多い外車が頻繁に持ち込まれるために、作業予定が空いていたのがちょうど僕がお盆で岡山に戻っていなくてはならない時期に重なっていました。ご覧のように四台も置けば一杯になる小さな自動車屋さんですから、僕が東京を離れる前にミニクーパーを持ち込んでおくことはできません。困った僕の様子を見ていたお店の方は、駐車場が近くならカギを預けて岡山に帰省していただければお留守の間に勝手に車を引き取って点検整備をして、終わったらまた駐車場に入れておきますという提案をしてくれました。これには僕は大喜びなのですが、初めての客で、しかもその店で買ったわけでもない車の点検整備をわざわざ余分の手間暇をかけてまでやって下さるという自動車屋さんが東京のど真ん中にあるという事実には心底驚いてしまいました。おそらくこれまでもこんな安くて古くて小さな外車などは扱ったことなどない、ベンツやアウディなどの大型高級外車を専門とする店にもかかわらずです。

こうして、西日本集中豪雨で我が家がどの程度の被害を被っていたのかをチェックするためとお盆のお墓参りのために、いつもよりも長く岡山に(といっても大阪に二日と岡山に三日滞在しただけですが・・・)戻っていた僕が白金に帰ってきたとき外観までもがピカピカに磨き上げられたミニクーパーを地下駐車場に見つけたときには感動しました。エンジンをかけてみると、半年前に購入したときよりもさらに軽快なエンジン音が響きわたり、見事に整備されていたことを文字どおり肌で感じることができました。
この高層オフィスビルの地下駐車場といい、外車専門の「鈴木オート」といい、まるで岡山から持ってきたミニクーパーのために予め用意されていたかのようです。レトロな東京を代表する港区白金ならではなのですが、それに加えて、そこに暮らして働く人々もまたレトロな人情をキープし続けているのです。
今度は気のいいお婆ちゃんがやっているレトロな飲み屋について語ってみたいと強く思う保江邦夫